太田おおたねっとからのお知らせ!!
ゆるぎかぶ(万木かぶ、萬木かぶ)
矢島かぶ
北之庄菜(北之庄かぶ)
日野菜かぶ
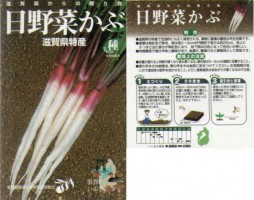
原産地は滋賀県蒲生郡日野町といわれ、蒲生郡と、隣接の甲賀郡で多く作られていたが、現在では県外の生産量も多い。
『日野町誌』によれば「日野菜は原と蒲生家の音羽城の附近、爺父渓(やぶそ)と称する地点の野生種にして葉及び根は紫紅色を帯べる蕪菁の一種なり 蒲生貞秀入道智閑、曽て爺父渓に在る観音堂に参詣せし時、見馴れぬ菜のあるを見て之を採り来り、試みに漬物となさしめしにその色澤桜花の如く艶美にて風味亦佳良なりしかば、野生しある地点を開墾し観音堂の僧に命じて栽培せしめたる菜を以て漬物とし之に一首の歌を添えて飛鳥井大納言雅親郷に贈れり。“ちぎりおきてけふはうれしく出づる日野菜とあかつきを恨みわびけんと”。
更に之を後柏原天皇(104代、1501~1526年)に献じ奉り喜ばせ給ひ、其の桜花に似たりとして桜漬と題された」とあり、『本草綱目啓蒙』(1802年)に「一種のあかかぶ一名あかな一名むらさきな一名日野菜一名近江なあり その葉油菜に似て紫色根長さ五六寸にして圓ならず色紫赤用てくきづちとなす江州日野の名産なり 他に移し栽ればその色変す」とありその後『證類本草引日華本草』『続江戸砂子』にも出てくる。
本種は他県には分布せず本県のみに現存している。
カブには珍しい長根で、径約3cmで長さ20~30cmになる。抽根部があざやかな紫紅色、下部が白色で、その色の対比が非常に美しい。
もっぱら漬物に加工され、独特の香りがあり、賞味されている。
葉は立性でわずかに欠刻があり、紫紅色をおびている。
保水力のある排水のよい土層の深いところが適している。
本種は、滋賀県農業試験場と地元日野町の篤農家の協力の下、滋賀県種苗生産販売協同組合が系統の選抜をやり直し、往時の純系に近づけたものである。
伊吹大根
坂田郡伊吹町大久保附近で古くより栽培されていた。
このダイコンは峠(トウゲ)ダイコン、マムシダイコン、ネズミダイコン等と呼ばれている。
『和漢三戈図会』(1713年)には「江洲ノ膽吹(イブキ)相洲ノ鎌倉共ニ鼠大根ヲ出ス形短而尾有味甚辛ク……」とあり、また『本草図譜』(1821)には「葉はダイコンに似て痩せ根も又細くして長さ一尺余上細く下太く根の先を切たる如くなることマムシの尾に似たり唯細き根を垂ること鼠の尾に似たりこれ全てダイコンの類にしてニンジンの類にあらず時珍ニンジンの条に入るは誤なるべし」、本朝食鑑に「鼠大根という者あり短かく円く豊肥して其尾細く長し故に名く其味極めて美なりといへり」と書かれ図は三色刷りで印刷されている。
また、後年の出版書ではこのダイコンから草津の山田、伏見の桃山、紀州の和歌山ダイコンなどが生れているが、当時種子は門外不出であったと思われることから、各地に分布したのは何者かが持ち去ったものと思われる。



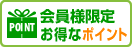
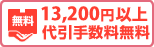
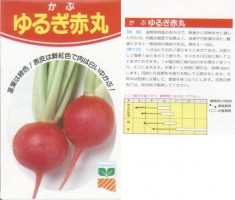
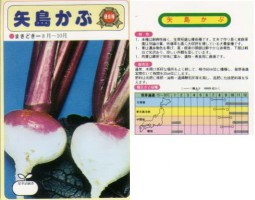
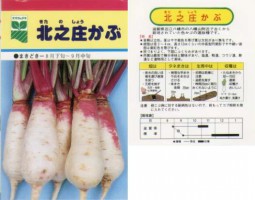


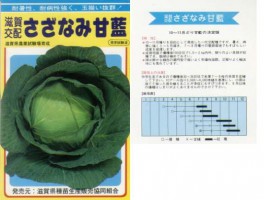
万木カブの産地において、根こぶ病の被害が年々増加し栽培上の問題となっていたため、滋賀県農業試験場では昭和56年秋に同湖西分場で選抜した万木カブの優良母本58個体を国の野菜・茶業試験場で鉢上げし、57年4~5月に病気に抵抗性のあるカブ4品種と交配してF1種子を得た。
その後、在来種との戻し交配をはじめ、現地の汚染圃場での抵抗性検定をはじめ、病土挿入法により幼病時の抵抗性検定を繰り返した。
また、実用形質については、草姿をはじめ根形、根色、肉質について調査し、当初の育種目標に近く特性の優れた系統について種苗登録を出願し、平成5年3月10日付で品種登録(登録品種名:湖西1号)された。
近江万木かぶのページへ>>